
-プロローグ 夢のスタートゲートへ-
スタート1時間前にPlace du Triangle de l’Amitiéに向かう。Chamonixを象徴するSaint Bernard du Mont-Blanc教会前は2000人超のランナー、大会関係者、そしてギャラリーでひしめき合っている。脇道でストレッチをしてから、この群衆に混ざった。

音楽とDJが会場を盛り上げ、否が応でも気持ちが高揚する。エリートランナーの入場が終わると、会場は異様な緊張感に包まれた。スタートの直前に大会のテーマソング『Conquest of Paradise』が流れる。ずっとこの場所で、この曲を聴きたかった。心が震える。空からは予報通り、律儀に雨が降ってきた。
「Une minute / One minute」。
一分前に一言だけ、アナウンスがあった。他の大会のようなカウトダウンはない。荘厳な『Conquest of Paradise』だけが広場に、Chamonixに響く。曲がピークに達するとき、なだれを打つように先頭集団が駆け出した。
2013年のUTMFで知ったウルトラトレイルの世界
UTMB(Ultra Trail du Mont Blanc, 174km 9900m D+)の完走は、私の夢の一つでした。私に限らず、このレースは多くのトレイルランナーが「人生で一度は」と思う大会の一つです。フランス・イタリア・スイスの国境を自分の足でまたぐスケールの大きさ、世界トップレベルのアスリートが集う最高峰の大会、開催中の熱狂的な大歓声。こんな大会は、世界中で類を見ません。
先週末の夕方、痛む両足を引きずりながら、「俺、こんなに遅かったかなぁ」とやや不本意なコースタイムで、最終ランナーに追われるように、ゴールを迎えながらも、無事「公式」にFinisherとなりました。ひとつ、ランナーとしての節目を迎えた感があるので、UTMBを目指してきたあゆみを振り返ります。

UTMBを初めて知ったのは、おそらく2013年の富士山の須走。当時、週末にマラソン大会の計測スタッフとして全国各地のマラソン大会に趣いていました。その仕事で、第二回のUTMF(Ultra Trail Mt.Fuji)に派遣され、泥にまみれながらも進み続ける選手たちの姿を目の当たりにしました。
その現場で先輩スタッフから、「本場ではMont Blancを一周する大会がある」と聞かされたのだと記憶しています。須走はレース序盤のチェックポイントだったので、初日に現場は解散となり、業務終了後にゴールの河口湖に行きました。着いた時には、トップ選手はとっくにゴールしていて、ゴールインするのは、かろうじて歩けているような、制限時間に近いランナーたち。仲間たちと笑顔で。ゴール手前から涙を流しながら。ゴールに向かって淡々と、着実に、一歩一歩……。100mileの旅路を終え、極限の疲労と歓喜、達成感がないまぜになった感情がそこにはありました。彼らの姿はより一層胸を打ち、涙が流れました。そして、こう思いました。「自分もやってみたい」。

でも、当時の私には富士山はおろか、モンブランなどまったく遠い世界でした。大学を出て仕事を始めたばかりで、その仕事もまだまだ板につかず。時間的にも経済的にもまったく余裕がありませんでした。

時間は少し進み、2018年の6月。場所はChamonix。いわずもがな、Mont Blancを擁するフランス屈指の山岳リゾートです。2017年の8月、当時東京で勤めていた会社を辞めて、ワーキングホリデー制度を使ってパリへ。その1年の締めくくりとして、フランス随一のロングトレイル・Tour du Mont Blanc(TMB)を10日ほどかけて歩きました。このTMBのルートは、UTMBで走るコースと重なっており、Chamonixを出発して、イタリア、スイスを超えてChamonixへ帰ってきます。
もう少しヨーロッパで暮らしたいと思いつつも多くの人にとって、一度日本に帰ったらもう一度戻ってくることはそう簡単ではありません。UTMBの出場は今の自分には難しいけれど、一度そのコースを体感してみたい。そう思って、この旅を企てました。

Mont Blancは、見る角度によって穏やかに、荒々しく表情を変えます。本格的な夏が来る前の山には、雪がまだ残っており、花が咲き乱れていました。ハイキングではありましたが、その距離感と山の大きさはしっかり体に刻み込まれました。「今度また来れるのはいつになるのかな」そう思いながらChamonixを後にしたのを覚えています。
Chamonix – Lac Combal okm – 69.3km
大歓声に囲まれてスタートゲートをくぐる。この大会の創立者の Polettiさんともハイタッチ。目抜通りのRue du Dr Paccardへなだれこむ。通りは村を出るまでギャラリーで溢れている。手を叩き、カウベルを鳴らして、歓声を送ってくれる。日本の国旗を見つけては手を振り、子供たちとハイタッチを交わす。こんなにドラマチックなスタートは、他にない。胸が高鳴り、笑顔がこぼれる。Les Houchesまではほんとがフラット。体を温めながら飛ばすエリアだ。2023年にTDSを走った時には、ゴール手前のこの林道がものすごく辛かったが、アルゼンチン人のランナーが先導してくれたことを懐かしく思い出す。
Les Houchesのエイドは水も飲まずにスルー。ここはほとんどのランナーがスキップするエイド。まだ水は十分にあるし、意外と厳しいと言われるLes Contaminesの24:00の関門を突破するのが先決だ。Saint-Gervaisまで早速600mほどCol de Vozaへの登りが始まったが、ここはこれから始まる累積10,000mの山登りへのアップに過ぎない。「81.5kmのCourmayeurまでは、抑えて後半戦まで温存」という基本戦略なのだが、スタート直後の興奮から登りきった後の下りはついスピードを出してしまう。サーフェスは硬めのグラベルで走りやすい。

山を下り終えると、Saint-Gervaisの村に着く。日が暮れて雨が降っていたが、ここでも大観衆が迎えてくれる。大きな声援が力になる。このエイドでも補給は軽めに済ませて、Les Contaminesへ。関門の約1時間半前の22:37に到着した。一つ目の大きな関門を超えて、ほっと一安心。ここでは時間をとって、エネルギーをチャージする。レースを通して初めてのアシスタント許可ゾーンということで、エイドはとても混み合っていた。サポートがいる選手たちを羨ましく思いつつも、これまでのレースもサポートなしでやってきただろう、と自分に言い聞かせる。
もう30kmを走っているが「UTMBはLes Contaminesを超えてから」とも言われている。ここを出たら2400mまで登り、Col du Bonhommeを超えるのだ。

エイドを出た直後、雨足が強く、体温の低下を感じたので、標高の高いCol du Bonhomme を見据えて、お店の軒先で防寒装備を着ることにした。ここから先、落ち着いて着替えができる場所はなさそうだ。体を濡らす前に対策を打つ。
走り始めると少し暑いくらいだったが、濡れて体を冷やすよりはいい。Les ContaminesからNotre Dammes de Gorgeまでの道はよく覚えている。2018年のTMBでは、冒険の始まりといった感じでわくわくしていた。2023年のTDSでは、レース終盤の明け方。Les Contaminesを目指して下り坂を走っていた。
UTMBでは、大会指折りのファンゾーンになっている。看板スポンサーのHokaが準備したネオンゲートと、熱狂的なギャラリーが、賑やかで背中を押してくれる。

登山道の分岐点でスタッフからコース変更の案内があった。Col de SeigneとLac Combal間のPyramides Calcaires が雪が積もり過ぎているため、削除されるということだ。夜で周りも見えなかったし、この変更で距離や累積獲得標高がそれだけ変わるか現場では分からなかった。でも正直やることは変わらない。山を登り続けて進むだけだ。
ここまでのナイトパートでは、緊張感を保っているのと何しろ暗いので、私のような単独ランナーは他のランナーと会話することもなく、淡々と進むことに集中できる。話したのは、エイドのボランティアの方々、あとは、フランス語がわからないランナーに、英語でコース変更について教えてあげたくらいだ。
他人とのコミュニケーションが少ない分、思考は内に向かう。まだ100数十kmも残っているというのに、もうゴールシーンをイメージして一人で泣きそうになっていた。色々な人たちの顔が浮かび、感謝の気持ちが溢れる。が、こんな前向きな感情は元気な時だけだ。
寒い寒いと聞いていたCol du Bonhommeだったが、TORでの反省を活かして導入した、Rabのダウンジャケットを着ていたら、寒さはまったく気にならず、気づいたら下り始めていた。足元は雪で白くなり、下りはぬかるみでずるずる滑る。転んでも怪我しないように慎重に下った。
Les Chapieuxには、04:02に到着。関門は05:15分。一時間の貯金は心許ないが、体力面の不安は全くない。Les Chapieuxからは夜が明けるので、気持ちも切り替わる。
ここまで眠気らしい眠気を覚えていないのは、睡眠マネジメントの賜物だ。6月末のLavaredo 120kで終始睡魔に襲われた反省を活かして、カフェイン断ちをした効果が出ている。コーラを少し飲んだだけで、コーヒーやカフェイン入りのジェルも摂っていないのに、眠くならない。スタート当日の昼寝も効いているようだ。
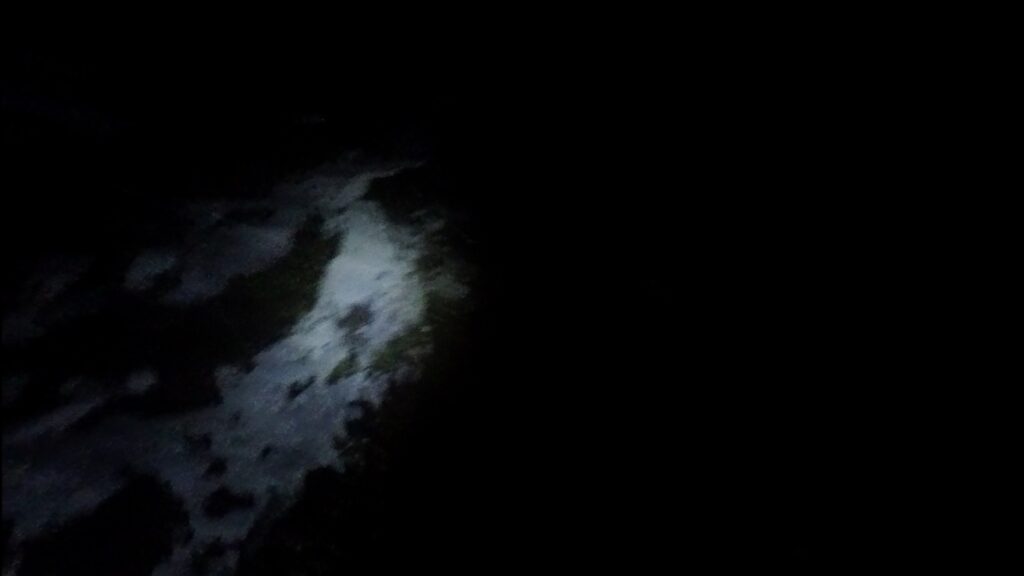
Col de la Seigneは、過去にも何度か通ったのだが、いつも雪が積もっていてうまく進めない。この日も雪と強風が吹き付けていた。幸いトレイルの泥は深くない。登りは遅いので随分抜かれたが、気にしない。下りで抜かせばいい、そう自分に言い聞かせる。
山頂に見覚えのある、登山道の常識が貼られたケルンが見えた。Col de la Seigneだ。ここからイタリアに入る。曇ってはいたが、ようやく見えてきた山の景色に気持ちが高まった。そうだ、このコースは絶景ルートなのだ。苦しい、キツイだけのレースではない。楽しまなければ。

谷間に流れる沢が見える。この沢はLac Combalに続いているはずだ。TMBでは、湖近くの山小屋に一泊した。コンパクトだが清潔な小屋だった。その小屋の庭でアイベックスの群れに遭遇して感動したのを覚えている。川に沿ってVeny谷を下ってしばらくすると、Lac Combalのエイドに着く。朝の8時過ぎ。関門は10:00なので余裕はある。1日を始めるために、温かい紅茶を飲んだ。

Saintéltonでの初トレラン出場からUTMBを目指す旅が始まる

UTMB出場を現実的に目標に据えたのは、2021年の12月フランスのLyonでのことです。
紆余曲折あり、2019年に再びパリに戻ってきて2年目。前回滞在時から仲良くしていたAdelineのパートナー・Maximeがトレイルランニングの大会、Saintélyonに誘ってくれたことがきっかけでした。この大会は2025年で71回を数えるフランスでもトレイルランニングの草分け的な大会で、総距離80km、累積獲得標高が約2100m。これだけ聞くと他の山岳レースと比べて簡単そうに見えますが(普通の人にはよく分かりませんよね)、この大会の特徴は、深夜0時スタートのナイトレースということ。それに加えて毎年雨、雪、泥にまみれる、寒さとテクニカルなサーフェスの攻略が鍵となるレースなのです。
初めてのトレイルランニングの大会ということで、一からギアを集め始め、おっかなびっくりスタート。この年も例年通りスタートから降雪。路面は凍結し、お尻滑り、泥祭り、体感温度は0°近くと、初めてのトレイルランニングにして、この競技で体験しうる悪環境の半分以上を経験しました。そして、意外にも完走できてしまったのです。その時に、「頑張ればUTMB完走は夢じゃない」と確信しました。
この日から、私のUTMBを目指す旅がはじまりました。
新型コロナウイルスが猛威を振るう中、UTMBを取り巻く環境も劇的に変化。UTMBグループ傘下の大会出場が半ば義務付けられる「ランニングストーン制度」が導入。要はポイントを集めると、抽選にかけてもらえる=ポイントが多ければ多いほど、当選確率が高まる、というもの。2022~2024年にかけて、ヨーロッパ各地で開催される“by UTMB”の大会を転戦し、“石集め”に奔走することになりました。
【Lac Combal-La Fouly 69.3km – 114.5km】

ここまで来たら、中間地点のCourmayeurまではあと少し。ひと山登るが、登り切ればあとは1000mのダウルヒルだ。TMBを歩いているのだろう、ハイカーたちに混ざって、山の頂上Arrête du Mont Favreまで登る。ハンディタイプの機械を持ったスタッフが「ハイカー、ランナー、ハイカー」と仕分けをしていた。バッグのタグを見せて「OK」をもらう。山頂に設置されたガラス製のコンテナの中には、疲弊したランナーが二人体を丸めていた。ここでリタイアしたら、自力で下るのだろうか? それともヘリ? いや、自分のレースに集中しよう。周りのランナーもペースを上げて山を下り始めた。

山頂付近のシングルトラックから、道幅が広がりグラベルに変わった頃に、眼下に山小屋が見えた。Courmayeurの一つ手前のエイド・Checrouit のMaison Vieille小屋だ。ここでは、パスタのサービスがあったのだが、Courmayeurで大休憩を取るつもりでいたのでコーラだけ飲んで進むことにした。ちょうど私の後ろにPollettiさんが駆け込んできた。奥さんとともにUTMBを創り上げたその人だ。70歳を超えたお爺さんがここまでやってきたことをリスペクトするのと同時に、40手前の自分はここにいていいのか? と不安になる。彼の到着を見届けてCourmayeurに降りた。

Chamonixからモンブランを挟んで反対側のこの村には何度も訪れている。トレイルから石づくりの無骨な村に入り、2024年にTOR出場時に宿泊した家を見つけた。エイドステーションのスポーツセンターは残り数百mだ。当時の記憶が鮮明に蘇る。Aosta渓谷のEaux Roussesというチェックポイントで、リタイアを宣言した翌朝、この静かな体育館でドロップバッグを受け取った。走ることを始めたから初めてのDNF。当時は、自分の準備の甘さを認め難くて、リタイアした判断を正当化していたような気持ちだったと思う。力を出しきれなかった悔しさという強い感情よりも、行き場のないもやもやとした喪失感が胸のあたりに広がっていた。
誘導のスタッフからに案内されて、空席を見つけて座り込む。目の前にいた若い女性は、電話をしながら涙を流している。ここでリタイアするのだろうか。私も自分のやることをやろう。エイドでのワンオペはアシスタントがついているランナーと違って、手間と時間を要する。まずは全装備の取り替え。私は気分転換のためにシューズからTシャツまで全て交換する。エイドステーションに更衣室はない。男性も女性も、物陰で少し隠しはするものの、多くの場合、その場で着替える。時間がもったいないし、疲労から恥ずかしいと感じる余裕もない。ウェットティッシュで、なるべく泥を落として乾いた靴下やTシャツを身につける。ゴミもひとまずは床に置かせてもらう。

着替えが終わったら栄養補給だ。パートナーに用意してもらったおにぎり、甘酒、自分で持ってきたカップうどん、果物ゼリーがある。胃の中を温めるために、うどんをチョイス。おにぎりは持っていく。入れたお湯がぬるくて麺が戻り切らない。硬いまま平らげて、甘酒やゼリーなどの流動食を流しこむ。
何にそんなに時間を使ったのか、正直分からない。いつの間にかスタッフから「あと15分でこのエイドは閉まります」と言われた。え、もうそんなに時間経ったの、と焦る。エイドワークの手際の悪さで、30分は失っただろう。本当は、メディカルチームに寄って、足裏のケアをしたかった。すでにマメが数箇所できているし、足の皮もふやけている。自己流で、市販のマメ用のテープを貼って、擦れ対策のクリームを足に塗りたくる。貴重な時間を減らしてしまったことから、Courmayuerを出た後気持ちは落ち込んでいた。
Courmayeurは、81.5kmと距離でいえば中間ではない。けれども累積獲得標高では既に4440mに達している。後半戦はじめの山場Grand Col Ferretを超えたら、登る山の標高も低くなり走れる場所も増えるはず。制限時間を気にしながらも、そんなことを自分に言い聞かせながら山道を登る。初日の曇天とはうってかわり、日が出ている。イタリア側から見るMont Blancはワイルドだ。山頂に雲がかかっているのが残念だが、深く切れ込んだ谷筋が幾重にも織りなしている。

登りを終えて着いたRefuge Bertonneは、飲み物だけを提供するだけの小さなエイドだ。昼下がりの午後、ランナーが昼寝をとっていて、レース中とは思えない長閑な雰囲気が漂っていた。私も小屋の陰に寝そべり、目を閉じて一休みする。

ここからBonatti小屋までのトレイルは、Grandes jorassesをはじめMont Blanc山群の名峰を臨む絶景ルートだと覚えていた。UTMBでは、Grand Col Ferretまで大きな登りはない、走れそうな区間だったが足のトラブルが出始めていて、スピードを上げることができず。Bonatti小屋のベンチでコーラを飲んで休んでいた韓国人のカップルを見て、「いいなぁ俺もコーラ休憩しようか」と邪念が浮かんだが、次の関門Arnouvazまではあと5km。水の補給だけにとどめて前へ進む。
99.8kmのArnouvazには、関門の45分前に到着。危ない危ない。あそこで彼らにつられていたら、カットオフされていた。休憩をそこそこに、医療班に足裏の皮のふやけ、そしてちぎれ、マメの処置をお願いした。処置しないとこの痛みで完走が危ない。他のby UTMBの大会でも同様のトラブルがあり、そのたびに医療班には世話になった。処置の正確さ、迅速さを信頼している。マメの水を抜いてから消毒。テーピングを施すことで、足裏の痛みが抑えられる。時間を使ってしまったが、Chamonixまで帰るには必要な時間だ。15分ほど、ベッドに横になれたので休憩もできた。

Grand Col Ferretに取り付く頃には、日が傾いていた。時々陰り始めたFerret渓谷を振り返り、その景色に息を飲む。登りはキツイけれど、この景色の中で挑戦できている喜びを改めて感じる。コルの前で、ヘリコプターがランナーを救助する珍しいシーンに立ち会った。おそらく捻挫をして動けなくなってしまったのだろう。爆風で接近したヘリコプターは着陸することなく、ランナーを引き上げて立ち去っていった。救助が終わるまで我々は、トレイルに伏せて待った。
Grand Col Ferretは名前の通り、大きかった。登りに弱い私は、何度も登りで立ち止まり後続のランナーに抜かされた。イタリアとスイスの国境のコルを過ぎればようやく、下りが始まる。10km。登りで時間を使った分を取り戻すべく、できる限りスピードを出す。足が止まり、完走を諦め始めたランナーを抜かしていく。
舗装路に降りて、「もうすぐ着くだろう」とエイドを探すがなかなか到着しない。女性ランナーと「あれかな?」「こっちかな?」と話しながら先へ進む。このエイドの直前の距離がもどかしい。ようやく、エイドが見えた時は、あぁそうだここだ。と思い出した。
La Foulyには、カットオフタイムの30分前に到着した。
ランニングストーンを集めながらトレランの経験を積む

フランス国内にby UTMBの大会は多くありませんでした。そのため、ランニングストーン集めには、外国の大会に行く必要があります。せっかく走るなら、日本からは行かなそうな、大会に出たいと思い、あちこちのレースへエントリーします。2023年は、スペイン、スイス、フランスの大会へエントリー。
スペイン、カナリア諸島のパルマ島のTransvulcania(72.7km 4600m D+)では、海抜0mから、2000m峰まで登らされて、再び海まで降りてくるという、鬼畜レースを経験。2000mという獲得標高がどういうものか、体(というより膝か)に叩き込まれました。てっぺんから後は降るだけなのですが、足が消耗してまったく走れず。

スイス・グリンデルワルドのEiger Ultra Trail(51km 3000m D+)では、50kmに出場。懐かしいEigerを眺めながら山の中を駆け回る楽しさを改めて知りました。調子がよく、上位1/3くらいに入る好成績でゴール。

ニースのUltra Trail Métropole Nice Côte d’Azur(165km 8400m D+)は100mileに挑戦。2022年に100kmカテゴリに出場したのですが、パリで知り合った友人と再び参戦。トレイル上で日本から来たランナーとも仲良くなりました。深夜に睡魔に襲われ、コンクリートの構造物の上で十数分仮眠をとったところ、寝起きに足が硬直してまったく動かせず、パニックになったのを覚えています。あと、さそりを森の中で見ました。案外小さいんだな、というぼけっとした感想でした。

実はこの年に、UTMBの一レース、TDS(Sur les Trace de Duc de Savoie, 145km, D+9176)にも出場しています。フランス滞在中に必ずUTMBに出れるわけではないと思い、挑戦してみました。このレースは抽選もなく、参加資格もいらないのです。距離こそ本家のUTMBよりも30kmほど短いですが、山岳地帯を多く通るコースレイアウトから、人によってはUTMBより難しいともいいます。初日の悪天候、二日目夜の睡魔に襲われつつも、40時間を切り余裕を持って完走。Chamonixでの感動的なゴールを経験し、自信を得ました。パリへ帰る前にUTMBのスタートを見届けて、「やはりこのレースに出なければ」と決意を新たにします。
2024年は、フランス、スペインそしてイタリア、そして日本へも。
2023年時点でランニングストーンを十分集めたので、この年はUTMBに出場するつもりでいましたが、なんと抽選に外れてしまいます。そのため、さらにストーンを貯めるべく、by UTMBの二大会、さらに失った夏の目標としてイタリアの200mileレースTOR(Tor des Géants 352km、 D+25,170)に参戦。UTMBには直接関係ありませんが、春には一時帰国の際に初めて日本の大会Mt.Fuji100(旧UTMF)の70kmカテゴリー、KAI(69km 3336m D+)を走りました。
KAIは、中学生くらいから毎年のように通った山中湖・河口湖が舞台。初めての日本でのトレランということや、懐かしさや嬉しさもあって、快走。278位/952位と、珍しく高順位でのフィニッシュ。

フランス・アルザスのUltra-Trail des Chevaliers en Région Grand Est(172.5km 6625m D+)は100mileレースで、雨と泥の中、足が豆だらけ。さらに皮がふにゃふにゃになり、よじれる中、なんとか完走。

スペイン・ピレネー山脈で開催されたHOKA Val d’Aran by UTMB®(42.6km 3614m D+)は、100mileレースでしたが、40kmを超えたあたりの尾根で、雷雨に見舞われレースが中止に。山頂で雷に打たれるか、低体温でダウンするかという極限の状況を経験しました。
日本でも有名なイタリアのTORでは、初めてのDNF(Did Not Finish)を経験。装備準備の甘さから、初日の悪天候に対応しきれず、気持ちを擦り減らしてしまった結果でした。
UTMB出場が決まった今年2025年は、憧れていたイタリア・ドロミテの大会Lavaredo 120K(120k 5800m D+)へ。フランスやスイスのアルプスの地形とまったく異なる、尖峰を擁する山々。美しい色を湛える湖。これまで走った山の中でもとりわけ美しい景色でしたが、エコノミープランで計画した旅程が仇となり、初日の夜から睡魔に襲われ、大ブレーキ。レースの半分以上を眠い状態で過ごし、何度もトレイルの脇に座りこんで仮眠をとりました。ゴール直前のエイドの横で倒れていたら、ドクターに捕まりリタイアされそうになったくらいです。辛くも完走しましたが、この経験から、カフェインの効果を最大化するために、UTMB本番まで一ヶ月半ほどカフェイン断ちを決行。本番での効果はてきめん。初日の夜はコーラ一杯で眠気を覚えることはありませんでした。
【La Fouly – La Flégère 114.5 – 168.4km】
La FoulyからChampex-Lacまでの10km弱はボーナスステージだ。全て下り坂で、グラベルと舗装路が大部分を占める。さすがにスピードアップして走った。足裏のトラブルはあるものの、走れる足はしっかり残してある。二日目の夜になり、多くのランナーが歩き始めていた。過去の何度かの100mileレースの経験から、登りやテクニカルなサーフェスは歩いても問題ない。でも、走れる区間をサボってしまうと、完走は遠のいてしまう。上りでかけた時間はしっかり取り返さなければ。記録を見返すと、La Foulyの下で1820位から50人、Champex-Lacに着くまでに、147人を抜かして1680位まで順位が上がっている。Finisherが1665人ということを考えると、ここで走るか走らないかは、大きな分岐点になったと思う。
TMBでは、Chmapex-Lacは明るい時間に来た覚えがある。夜の景色に中だと過去の記憶となかなか重ならない。たどって来た川の先に湖があるのかと思っていたが、Issertという集落を抜けて山に登り始めた時には、どこに湖があるのか不安になった。このトレイルに、Champex-Lacの案内が出てきて、なぜかトレイルにはトーテムポールのような木彫りの彫刻が立っていた。
Champex-Lacのエイドは湖の手前だった。一所懸命走ったおかげで、一時間以上の貯金を増やすことができた。
中に入り、さて、何をしようかとぼけっと立ちすくしていると親切なボランティアが声をかけてくれた。「ベッドがあれば仮眠をとりたい」と言ったが、まずは座りなよ、とベンチを案内してくれた。アシスタントがあるエリアで日本の方も「誰か探していますか?」と声をかけてくれた。周りを見渡して、しっかり休憩をとる。ボロネーゼが美味しくて、元気が出た。
何組か日本人のグループを見かけたが、そこに井原知一選手と南圭介選手がいた。TDSに出場していたのは知っていたが、ランニングチームのサポートに来ているのだろうか。なんて、贅沢なアシスタントだろう。補給を済ませたら二回目の夜に備えて15分ほどテーブルに突っ伏して仮眠をとった。睡魔というほどの眠気はない。でも、疲労は溜まっていた。たまたま席をとったテーブルの後ろの席に、私と同じザックを使っていたランナーがいて、そこに座ろうとして、ザックをまじまじと眺めた。おや、何か違うな。そう思っていたら、彼のサポートだろう、向かいに座っていた年配の女性に「これはあなたのじゃないよ」と言われてしまった。「ごめんなさい、疲れていて。あっちか」とぼやいて自分の席を見つけた。
念のためにコーヒーを一杯飲んでChampexを出る。次の関門は5km先のPlan de l’Auという場所。カットオフタイムだけが示されている。登りに入る前の林道で、イタリア人の若い女性ランナーの撮影部隊が5名くらい、照明を持って現れた。彼女に声をかけながら、ムービーとスチル両方を撮影している。彼女とはしばらく同じペースだったので、一定区間この照明を浴びせられた。はて、彼女は有名人なのだろうか? 彼女が何者かに興味が湧かなかったが、彼女の他にも撮影チームを組んでいる選手は何人か見かけた。確かに、一生に一度くらいの挑戦だ。他の大会ではこの光景は見ることはない。
Champex-Lacからの登り勾配が激しく細い。道が詰まる中、遅い選手を抜かして登っていく。Plan de l’Auがなかなか見つからず焦り始めた。山道にエイドがあるはずもなく、コルでタグをチェックするような、ポイントなのかな、と思いとにかく登る。カットオフタイムが近づいても、まったくチェックポイントがある気配がしない。状況がわからず、軽いパニックになっていた。もしかして、チェックを受けないまま通り過ぎてしまったのか? それともこんなところで、リタイア? 情報を集めようと、まずは近くにいた日本の方に「Plan de l’Au、通りました?」と尋ねる。その方は、関門の名前と時間を覚えておらず。次にフランス人を見つけて聞いてみた。彼は「同じ疑問を持ってたんだよ」と言って、答えてくれた。携帯のmapで調べたらしくどうやら我々はそのポイントを既に過ぎているようだった。スタッフもいなかったし、チェックポイントもなかった。何のためにあったのか、分からないと彼も言っていた。今でも不思議に思うのだが、あのポイントは何だったのだろう? 彼の言葉に安心して、登りのペースを落として進んだ。

Trientまでの山は2000m弱の樹林帯の中。夜なので無理をせずに歩きに徹した。二日目の睡魔にやられたランナーがばたばた倒れていく。登山道の横で潰れてしまった女性もいた。ようやく、山を下り始めて、谷にTorientの集落が見えて来た時には空が明るくなっていた。鳥の声が三日目の朝を告げる。ここまで来た、お昼過ぎにはChamonixに着いている、はずだ。ピンク色の印象的なTorientの教会を過ぎたのは、7時10分。制限時間は8時。関門がまた迫いかけてきた。下り坂で傷み始めた足首を見てもらおうか、迷ったが貯金の少なさを考えてスルー。補給を済ませてVallorcineを目指してエイドを後にした。
そして、Chamonixへ

レースも終盤、さすがに焦っていました。関門ぎりぎりのグループには、独特の諦めムードが漂ってきます。進んでいるけど、まったくペースが上がらない。ここで彼らと同じことをしていたら、自分も関門の波に飲み込まれてしまいます。150kmも走って、あと20km残してリタイアなんて、悔やんでも悔やみきれません。痛む足首を騙しながら下りで飛ばします。
スイスからフランスへ入るVallorcineに着く前、知人のランナーを励ましに登ってきたのでしょう、トレイルランナーの井原知一さん(トモさん)が駆け上がってきました。私のゼッケンを見て、日本人だと認識。「いけるよ、絶対間に合う!」と声をかけてくれました。めちゃくちゃ嬉しかったし、すごい勇気をもらいました。
“ラスボス”のLa Flégère。最後までしっかり900m登ります。絶対行ける、と信じていてもここで倒れてしまうランナーもいます。とにかく、前へ、前へ。少しでも自分よりペースの遅いランナーは抜かします。残りの5kmが遠い。5kmなんて街では30分もかからないのに、山では1時間以上。頭の中でペースの計算しながら、走れるところは少しでも走る。森を出てロープウェイの駅を上の方に見えると、そこがゲレンデだと分かりました。斜度がきつい砂利道。数百m先にあるゲートがはるか遠くに思えました。15分ほどでしょうか。ポールを掴んだ腕を使って、四足歩行で何も考えずに体だけを動かしました。

最終エイド・La Flégèreに着いた時にはもうゴールしたような安堵感。谷を挟んで向かいには青空にMont Blancが聳えていました。「よく頑張った!」日本の方に声をかけてもらい、思わず笑顔がこぼれます。ここに制限時間内に辿り着いたランナーは公式に“Finisher”認定されます。「あとは下りで一時間くらいだよ」とエイドのスタッフが教えてくれましたが、無理をした足首が痛い痛い。走ることはおろか、ふつうのハイカーよりも遅いくらいです。
Flégèreまで、抜きつ抜かれつしていたランナーたちに追い越されながら、とぼとぼChamonixまで降ります。ある段階で降りてくるランナーがいないことに気づきました。あれ、もしかして最終ランナーになっちゃう? あれは目立ちすぎるので、避けなければ。えっちらおっちら降っていると、案の定、スタッフに囲まれた最終ランナーが後ろに迫ってきました。

うお、やべぇ。スタッフに時間を尋ねるともう公式の制限時間間近。ラストプッシュ、行くか。坂道がゆるくなってきたところで、比較的足首が傷まない着地方法を探しつつ、地面を蹴ります。山から抜けるとアルヴェ川沿いのウィニングロードへ。ここまで来れば、沿道の方々の声援が背中を押してくれます。
「Merci, thank you, ありがとう」いろいろな言葉で沿道に感謝を伝えながら、村を駆けます。
Flégèreでバッテリーが切れて連絡できなかったパートナーを見つけて、一緒にゴールへ。ゴールする時の打ち合わせをしていなかったので、直前でわちゃわちゃ。最終ランナーが来ていたので、正直焦っていました。2023年のTDSの時はゴールしてからしばらく、ゲートでゆっくり写真が撮れたのになぁ。とはいえ、終盤のランナーへの温かい声援もトレイルランニングの醍醐味。ボランティアが作ってくれた豪華なゲートをくぐって、私のUTMBは終わりました。
タイムは46:55:05。
順位は、後ろから3番目。
もうちょっとかっこよくゴールしたかったな、という気持ちはありますが、100mileレースは完走できればいい。
というか、完走だけで十分すごいんです。

-エピローグ
40歳を前にして大きな目標を達成できて満足しています。初めて完走した2012年の東京マラソンから、随分長い距離を走れるようになりました。自分に全く自信がなかった当時から、走ることを通じて小さな自信を少しづつ積み上げてきたような気がします。
そして、次にどんな大会を走るのか考え中です。
勝負できる50kmのカテゴリでちょっと順位を上げてみようか、とか。リタイアしてしまったTORへのリベンジ、とか。大きな大会じゃなくて、ヨーロッパの小さな大会を転々と走ってみるか、とか。のんびりゆっくり歩くロングトレイルスタイルに切り替えるか、とか。筋トレの名目でやっている、クライミングを本格的にやってみる、そんなことを思い浮かべています。
でも、せっかく100mile走れる足があるんだから、このカテゴリを走ることは続けようとは思っています。経済的にもフィジカル的にも負担が半端ないので、年一くらいで。このエクストリーム感、今のところ100mileでしか得られない中毒性があるのです。
その土地の空気を全身で感じながら、自分の足で旅をする。
これまでと同じように。でも、ちょっとペースを落として。
そんな感じで、これからも走ることを続けていこうと思っています。
Tsuyoshi Kaneko

フランスを中心にヨーロッパでのハイキング、トレイルランニングなどの外遊びにまつわる情報を伝えるサイトです。また、毎月パリ近郊でランドネイベントを企画・催行しています。








